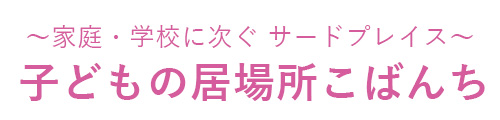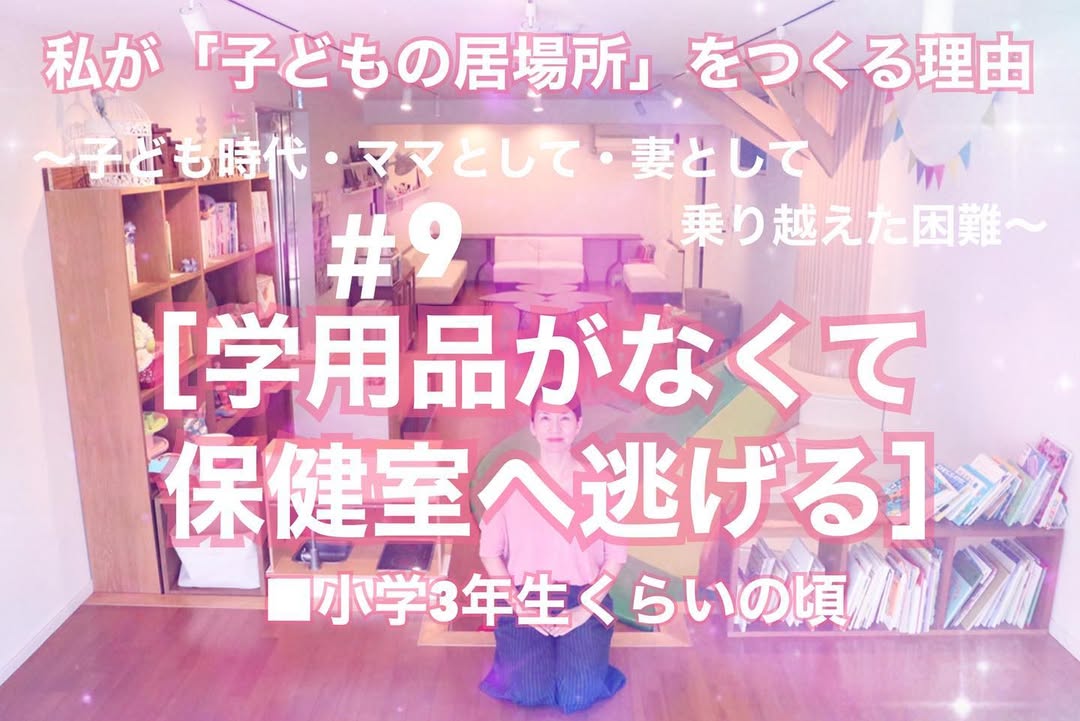~子ども時代・ママとして・妻として乗り越えた困難~
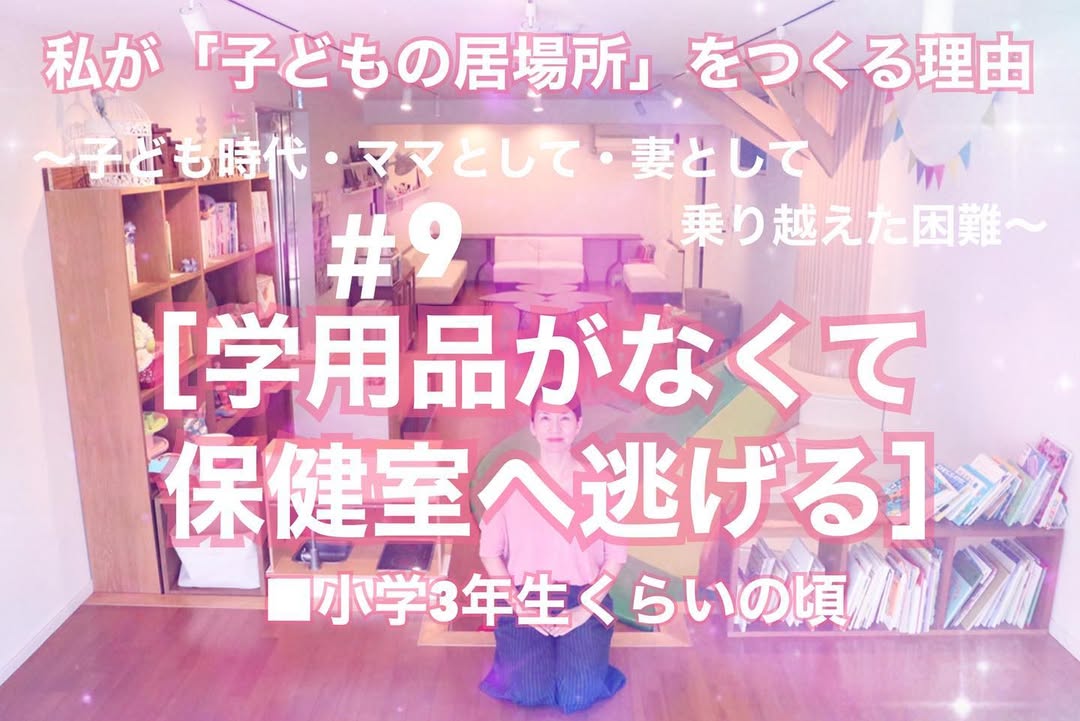
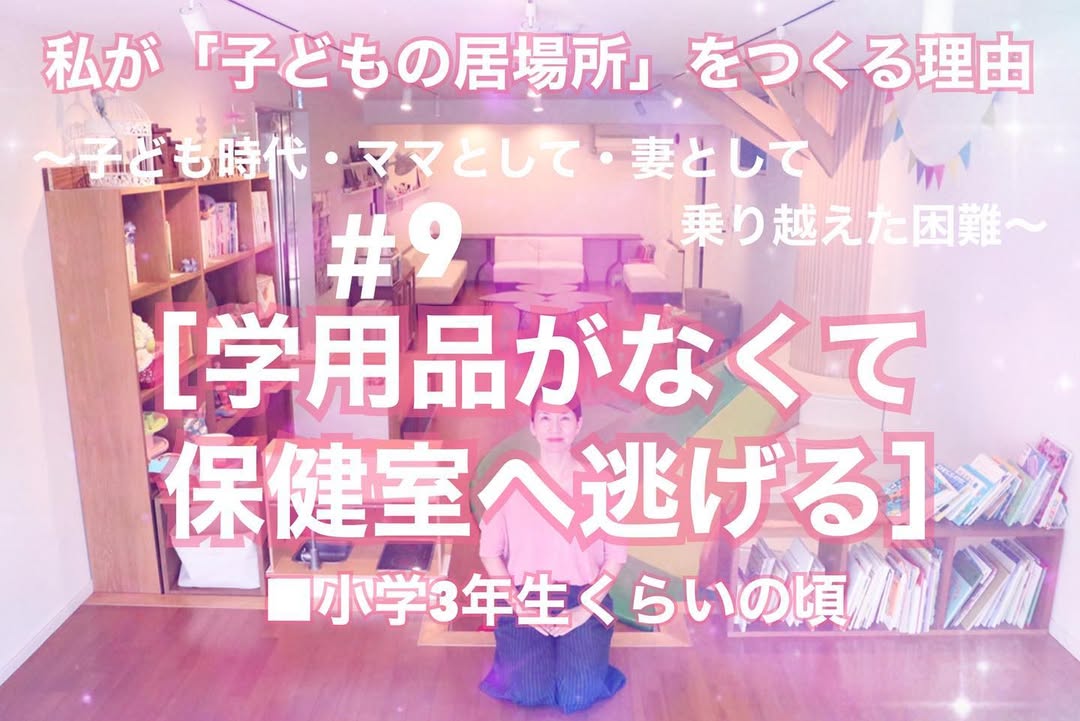
~子ども時代・ママとして・
妻として乗り越えた困難~
■小学3年生くらいの頃
[学用品がなくて保健室へ逃げる]
私の母は、酒乱の父のお世話に専念していたため、子どものお世話は後回しであった
私の学校準備を教えてくれたり、寄り添ってくれる人はいなかったため、忘れ物はあたりまえだった
その事に問題意識はなかったのだろう
先生の言葉と表情で『これは間違っているんだ』と気付かされる
---
図工の授業が始まり、先生が教室に入ってきた
私は何の迷いもなく先生の元へ行き
「お腹が痛いので保健室に行ってもいいですか?」という
先生は怒った顔をしながら低い声で
「忘れ物をするとお腹が痛くなる便利な体ね」
…と言い 顔を背ける
私はそのままの足で保健室に向かった
先生の言葉と表情の意味をひとり考える
私は自分で『忘れ物をすると保健室に逃げる』という自覚が まったくなかった
ただ、絵の具セットがないと図工の授業2時間は何もできないという事を理解していて、習慣的に保健室に逃げる方法を身につけていたのだろう
自分の行動が間違っている事に気付かされる
『私はなんてズルイ子なんだろう』
『ちゃんと絵の具セットを準備できない悪い子なんだ』
…と、他の子にできて自分にできないという 劣等感が積み重なっていく
---
この時の先生の表情はよく覚えているが、先生の特定を防ぐためにあえて『3年生のくらいの頃』とあいまいにしている
大人になって振り返ると
『先生、その事に気づいているなら他の関わり方があったんじゃないですか?』
って思う
今の学校は、担任や校長の方針によって異なっているのかもしれないけれど、突き放し型ではなく 寄り添い型が増えて
家庭に困難があり保護者の協力が得にくい場合にも「とにかく学校に来てくれればあとはフォローします」という体制をとっている学校がある事も知っている
うちの子が現在通っている学校も、我が子から「明日紙コップが必要」などと急に言われて困っても
「なくても大丈夫!先生が少し用意しててくれるって言ってた」と子ども自身が教えてくれて、先生の気づかいを感じる機会が増えた
---
先生達のフォローに感謝しつつも、学習ノートなど自分で用意しなきゃならないものは いまだに多くあって
私が子どもの頃は近所に文房具屋さんがたくさんあって、必要なものがあれば親からお金をもらって自分で買いに行くことができていたけれど
残念なことに今は、どこの文房具店もなくなってしまい、学用品の購入のために 車を出してショッピングセンターまで行かなきゃならないこともある
昔に比べて、保護者の介入や負担が増えたように感じる
子どもも前もって言ってくれるとは限らず、私もマメにチェックしているわけではないので
日曜の夜に
「絵の具の黄色がもうないけど、明日必要」などと言ってくる
「もっと早く言ってよ」
と私ブチギレる
---
昔のように、子ども達が自分の足で必要な学用品を手に入れられる環境をつくりたいと コドイバで事業計画中である
今は子ども達が楽しめるようにと 駄菓子の販売のみだが、少しずつ学校で必要な文房具の販売も始めようと思う
お小遣いをもつ子達は自分のお金で購入するが、お小遣いを持たない子達にはお手伝いや学習などのミッションクリアで購入券を手に入れられる仕組みをつくる
『画用紙1枚から買える場所』
『自分足で買いに行ける場所』
『自分の力で手に入れられる場所』
…を私はコドイバでつくる
子ども達1人ひとりが、問題解決能力を育む環境をつくろう
---
では次回は
■小学4年生の頃
[集金袋]
のことをつづります
またみてね!
-------------
このブログは、私 小林が2020年10月から「子どもの居場所」活動を始める至った経緯を綴ります
発信する目的は、多くの人に 私自身の事と活動を知っていただき、子ども支援の輪を広げる事です
今は「子ども」に特定していますが、今関わっている子ども達が大人になっても「自分の居場所」として帰る場所の一つになるように
また、支援者の仲間たちが集い、子ども達の成長を見守る拠点の一つになれるように、実績を重ねながら対象の幅を広げていきます
当活動を通して、子ども支援に関心を持っていただけないでしょうか
企業や個人の皆様からの支援を広く求めております。子ども達が安心して過ごせる、第三の居場所づくりの応援をよろしくお願いいたします